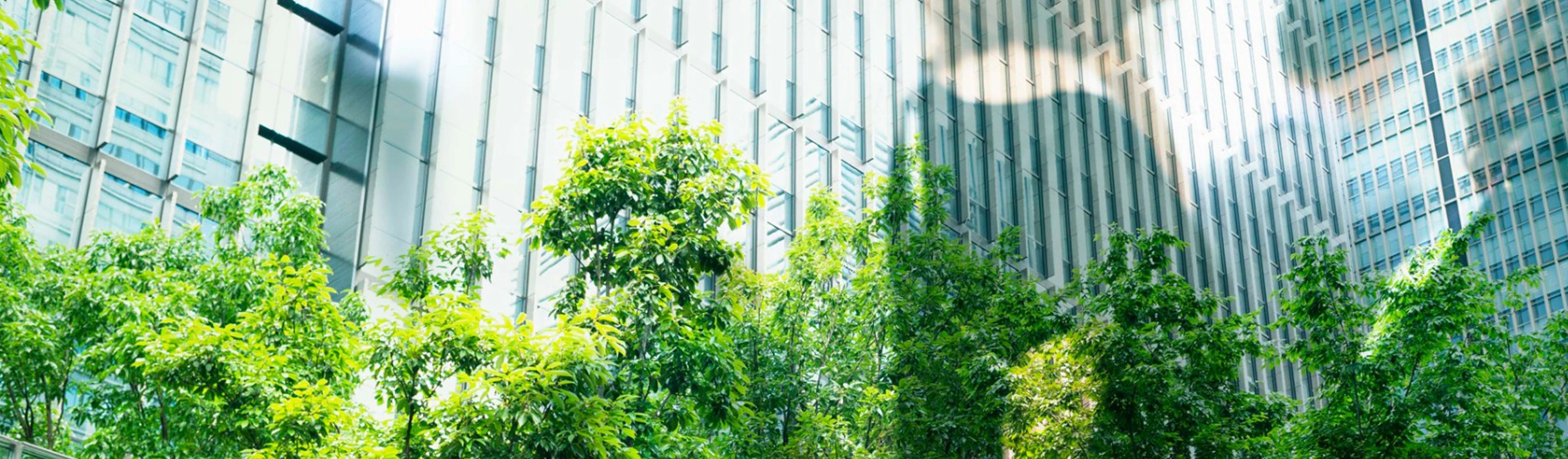
公共・社会インフラ
Government and Infrastructure
パブリックコンサルティングの力で
日本を「社会課題解決」の先進国へ
労働人口が減少するとともに税収も減り、公共サービスやインフラ整備にかつてのような水準が期待できなくなった今、行政や公的機関のみならず民間企業まで巻き込んだ総合力で「全体最適化」に取り組む必要性が高まっています。日本の社会課題そのものである公共セクターの課題に挑み、あらゆるリソースとプレーヤーを総動員して解決に臨むEYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社(以下 EYSC)公共・社会インフラセクターのコンサルタントたち。ユニットをけん引する村上パートナーに組織の使命と求める人材を聞きました。
「全体最適」を求めて日本の社会課題に立ち向かう
「社会課題解決先進国」の体現を標榜しておられます。背景をお聞かせください。
周知のように日本社会は少子高齢化によって急激な労働人口の減少に直面しています。稼ぎ手が減れば、市場は縮小し、内需がますます落ち込みます。日本の資産の多くは不動産に投資されますが、その資産価値も下落し、様々な局面でデフレ圧力が一層強まることになるでしょう。これまでのように人口増加とこれによる右肩上がりの経済成長により維持されてきた基本的な資本主義社会の仕組みが、もはや機能しなくなりつつあるのです。
労働力が減少することは税収の減少を意味します。その結果、インフラ整備が遅延するなど影響が及び、公共サービスの質の低下も避けられなくなる。ならばコストを削減すればいいとする議論もありますが、それだけでは本当の意味での課題解決には至りません。人口や需要は増加するという前提が崩れ、これによりGDP拡大を目指す従来の方法論が通用しなくなってきた以上、公共セクターにおいてもまた、各種の政策や制度や業務のあり方を設計し直す必要があるのだと思います。
そのように考えると、公共セクターが見据えている課題は、日本が抱える社会課題そのものだといえます。私たちは、ここに焦点を当ててコンサルティングサービスを提供している専門ユニットです。
コンサルタントとして、どのように解決策を導き出したらよいのでしょう。
人口拡大期においては、事業主体ごとに解決策を講じるような、個別最適化の手法が効率的で効果的でした。したがって大きな組織では縦割り構造が好まれ、横断的な連携は好まれなかったのでしょう。しかし、今は違います。行政の力だけでは課題解決が困難であるというのが現実です。官と民、業界や業種、社会全体と地域社会、さらには専門領域の垣根さえ乗り越えて、あらゆるプレーヤーとの協業で全体最適化を図らなければなりません。
あらゆるプレーヤーを結びつけ、最大価値を生み出すためのけん引役となることが、われわれコンサルタントが果たすべき使命です。そのために、この公共・社会インフラユニットでは、中央官庁や地方自治体、公的機関といったパブリックセクターをクライアントとしながらも、各界の民間事業者や専門家とも横断的に連携して、公共事業に関する様々な課題解決をサポートしています。

目先の利益にとらわれず「長期的価値」を追求
具体的にはどのような体制でプロジェクトに臨んでいるのでしょうか。
現在は次の5つのチームを主体に活動を展開しています。
まず、①GPS(Government Public Sector)チーム。ここでは官公庁や自治体、公的機関などの変革を支援することを目的に、防災・消防などのレジリエンスや、健康・医療労働関連といった社会保障を対象とするサービスなどを展開しています。
次に、②Infrastructureチーム。不動産や建設、鉄道、運輸・物流、観光といった、われわれの生活と密接に関係する公共性の高い分野を中心に、社会インフラを担う企業等をサポートします。公共セクターとの関係も深いため、このユニットで一括して担当しています。
そして、③SA(Social Agenda)チーム。ここでは官民連携のスキームを推進し、官公庁や自治体、公的機関などと民間プレーヤーをつなぎ、テーマカットで社会課題解決型ビジネスを展開します。地方創生の支援もここの守備範囲です。
これら3チームを主軸としながら、さらに新しい柱が加わりました。
その1つが、④Local DXチーム。コロナ禍で浮き彫りになったデジタル化の遅れを取り戻すべく、地方自治体向けにDX支援を進めているチームです。政府が主導するデジタル田園都市国家構想への参画などもサポートします。
最後に、⑤Sportsチーム。スポーツはする側にも観る側にも人々に活力をもたらす効果があります。そこに着目し、地域の活性化や人々のウェルネス、ウェルビーイングに資するさまざまな事業を支えるユニークなチームです。
社会課題は極めて広範囲にわたりますから、社会事情もにらみながら絶えず柔軟に組織を組み換えていく必要があります。これら5つのチームも決して固定化した存在ではなく、メンバーの関心領域や得意分野に応じて柔軟に拡充を図っていくつもりです。
この分野におけるEYのアドバンテージはどこにありますか。
EYが世界共通のパーパス(存在意義)として「Building a better working world〜より良い社会の構築を目指して」を掲げていることは大きいと思います。目の前の短期的な利益のみにとらわれず、時間軸を大きくとって長期的価値(Long-term Value)を追求することで社会平和を希求する姿勢。それはとりもなおさず、社会課題解決そのものを究極のミッションとする事業体であることを意味します。
他の大手ファームにも社会課題や公共セクターに関わるチームはあるはずですが、多くの場合、業界や機能ごとに区切られた組織の中でそれぞれ個別に対応しているのが実情だと思います。われわれは公共セクターの抱える課題を起点として、社会課題と直接的に向き合うことを目的とする、この業界でも極めてユニークな存在です。いきおい、頭一つも二つも抜き出た強みがあるものと自負しています。

あらゆるプレーヤーをつなぐハブであれ
メンバーで共有している役割、姿勢についてお聞かせください。
コラボレーション型で課題解決に当たる姿勢が大事だと考えています。先ほども触れたように、公共セクターが抱える社会課題に個社だけで立ち向かっても十分な成果は期待できません。例えば、ひとつのITサービスを提供するにも、社内のユニット/チームを横断するだけでなく、さまざまな強みを持つ外部のITベンダーや民間機関の力も結集して総合力で最大価値を導き出す。われわれコンサルタントがそのハブとなり、全体をまとめ上げる役割を担うわけです。もちろん、世界4大ファームとしてのアセットを生かしたグローバルな連携も必須です。
また、われわれの行動規範は常に、先ほど挙げたパーパスにあります。顧客の課題を解決するのは、より良い社会を構築するためであり、それは社会課題の解決に資することにほかなりません。したがって、あらかじめ決められたソリューションありきで利益を追求するようなコンサルティングとは一線を画しています。
そうしたマインドセットを持つ人材を求めているわけですね。
日本の課題に対して関心を抱き、問題意識を持っていることが第一。その上で、「自分だったらこうする、こんなことはできないか」といった自分なりの考えを持ち、解決に向けて行動を起こそうとする意欲のある方と働きたいと願っています。
その際、自分の強みとなる専門性を持つことは大切です。われわれのような業界担当のコンサルタントは業界の知識さえあればいいわけではありません。課題解決のハブとなるべき人物に専門性がなければ、クライアントは信頼してくれないでしょう。
その一方で、自分の守備範囲に閉じこもるコンサルタントもまた信用されません。一人ですべての領域をカバーできない以上、多種多様な専門家と協働することは必須であり、社内はもとより領域を問わずに絶えず誰かと手を組んでほしいですね。同時にまた、自分自身の中でも幅広いジャンルに目を向け触手を伸ばしてほしいと思います。縦軸の専門性と、横軸の展開性を持つ。私はこれを「L字型」の人材と呼んでいます。
私たちコンサルタントも市民の一人です。自分が解決した成果は自分自身に返ってくる。そのことを胸に刻んで、ともに日本を「社会課題解決の先進国」へと先導しましょう。




